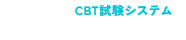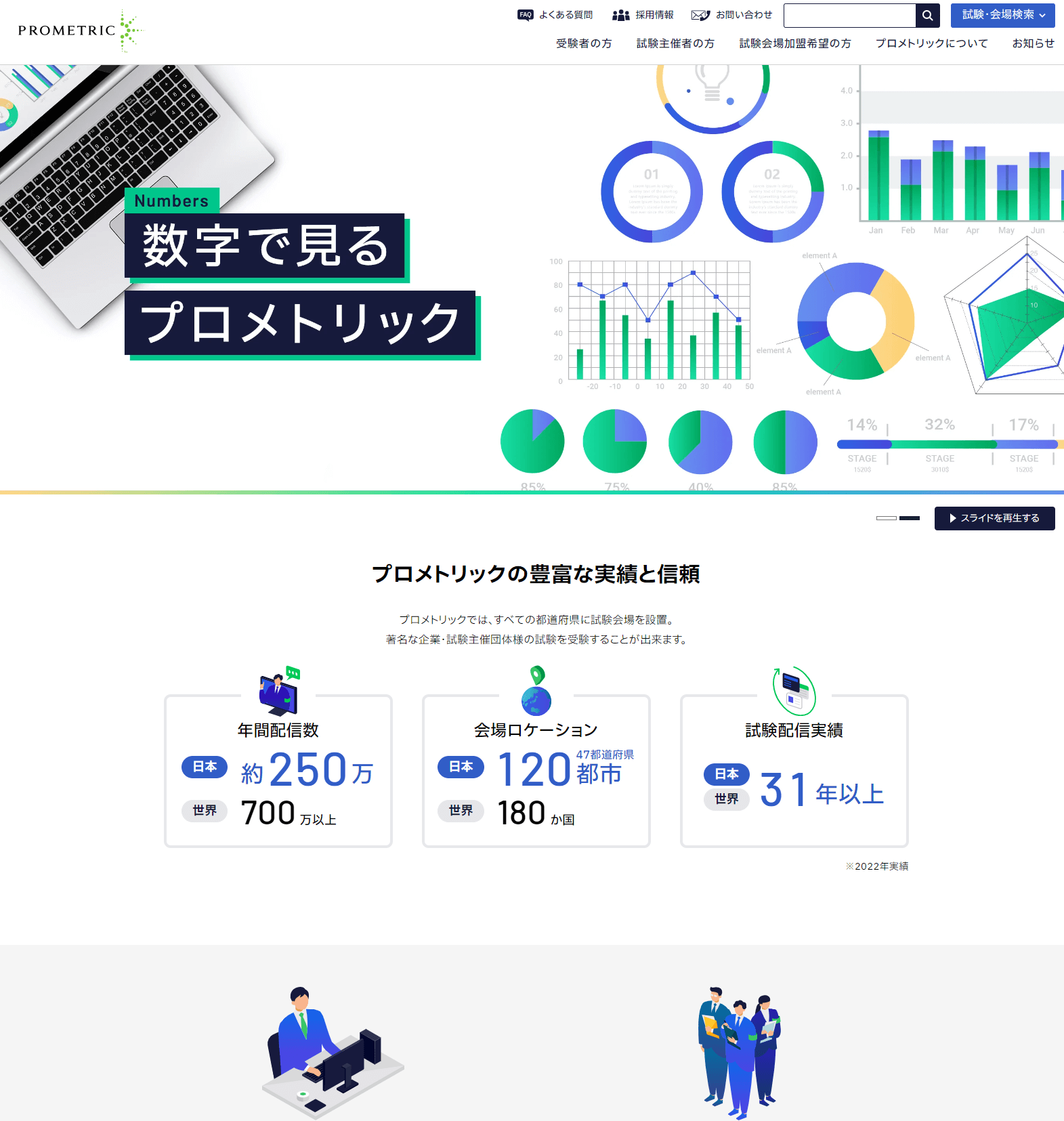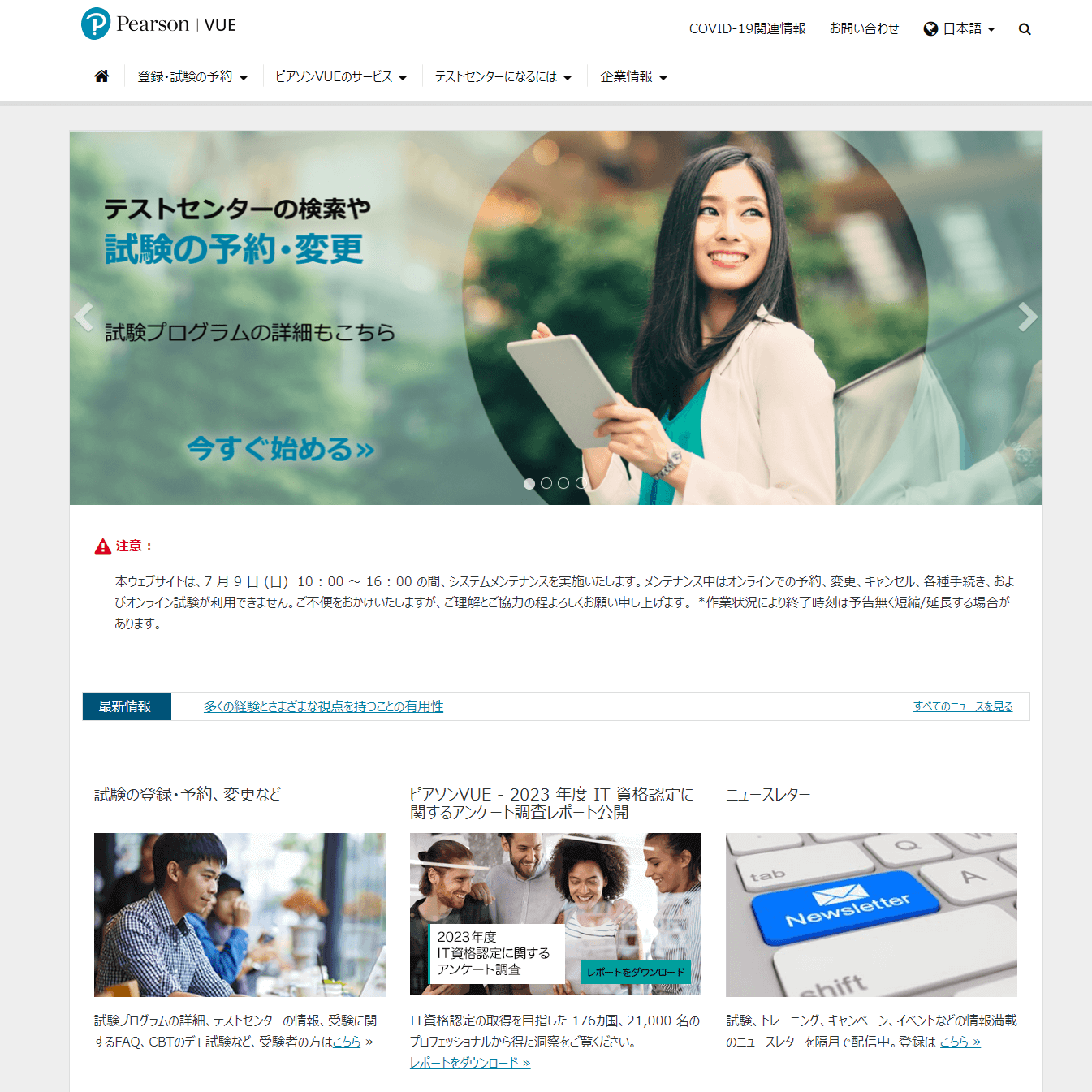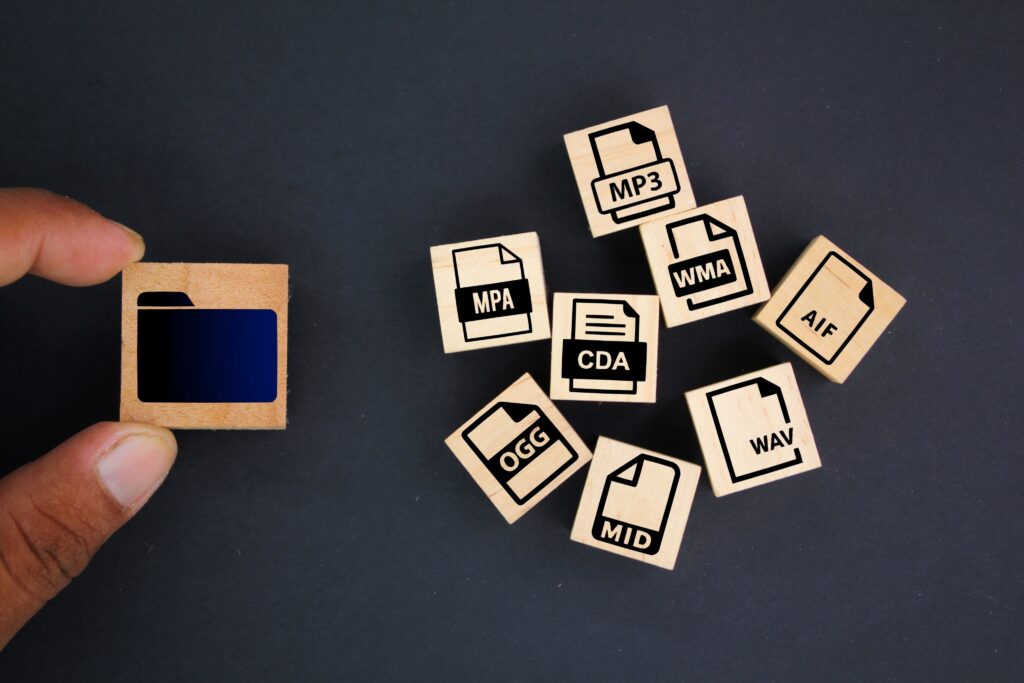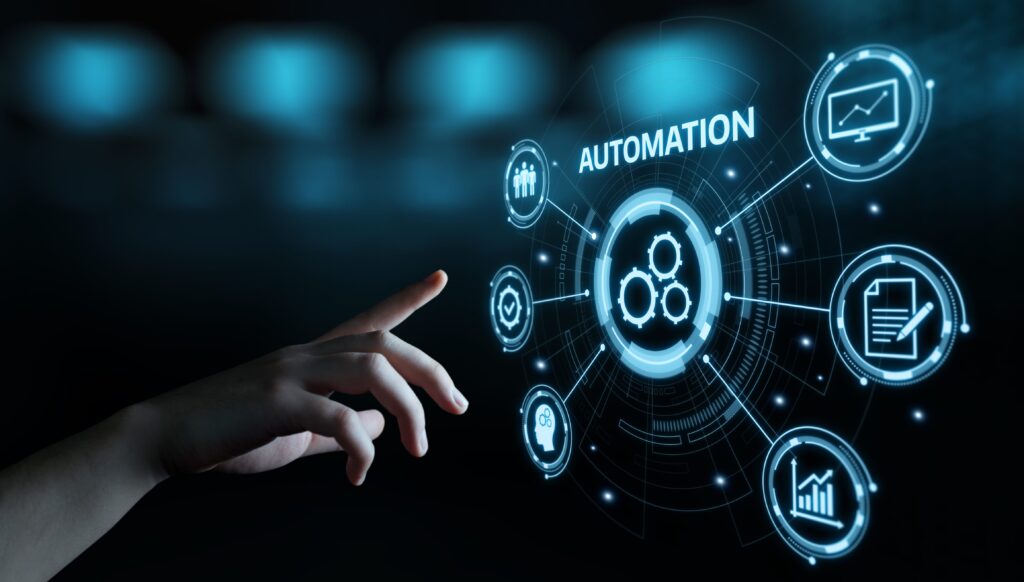近年、大学や企業を中心に広がりを見せる「オンライン試験」。パソコンやタブレットを活用し、自宅や会場で受験できる柔軟な仕組みとして注目を集めています。本記事では、オンライン試験の基本からメリット・課題、導入のポイントまで詳しく解説します。
CONTENTS
オンライン試験の基本と導入背景
オンライン試験とは、従来の紙やマークシートを使った試験に代わり、パソコンやタブレットなどのデジタル端末を用いて受験する方式です。実施形態には、指定会場にある端末を使用する「CBT(Computer Based Testing)」と、自宅などでインターネット経由で受ける「IBT(Internet Based Testing)」の2種類があります。
CBTは試験環境が統一されており、監視体制もしっかりと整えられるため、公平性や信頼性が高い点が特長です。一方のIBTは受験者の負担が軽減される反面、不正対策や通信トラブルといった課題も多く抱えています。
特に高い公平性や信頼性が求められる試験においては、CBTの優位性が明確です。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、IBTの導入が進んだ背景はありますが、安定した試験運営や厳正な評価という観点からは、CBTのほうが適している場面も少なくありません。
オンライン試験の主なメリット
オンライン試験の利点は多岐にわたります。導入を検討する担当者にとっては、実施者側・受験者側双方にメリットがある点が魅力です。
まず注目すべきは「受験機会の拡大」です。特定の会場に出向く必要がなくなるため、地理的な制約を受けにくくなります。仕事や家庭の事情で遠方の試験会場に足を運べなかった人や、国外に在住している人にとっても、受験のハードルが大きく下がります。
次に挙げられるのは「コスト削減」です。会場費や人件費、印刷コストが不要になるほか、感染対策にかかる費用も不要です。受験者にとっても交通費や宿泊費などが不要になるため、金銭的負担が軽減されます。
さらに「感染症対策」という観点でもオンライン試験は有効です。受験者が自宅で試験を受けることができれば、密集や移動による感染リスクが減少します。試験実施側にとっても、安全かつ安定的な試験運営につながるでしょう。
運営側・受験者側の双方に一定の利便性が求められるなかで、特に試験の正確性や公平性を担保したい場合には、CBTがより安定した選択肢となるでしょう。
オンライン試験における課題と不正対策
オンライン試験には多くのメリットがある一方で、「不正行為の防止」が大きな課題として挙げられます。会場試験のように監督官が常駐できないため、なりすまし受験やカンニングなどの不正をいかに防ぐかが問われます。
この課題に対し、近年は多くの技術的な対策が登場しています。たとえば、遠隔監視では受験者の映像や音声をリアルタイムで確認し、不審な行動がないかチェックします。受験中の画面共有やマイク使用を通じて、監視精度を高める取り組みが進んでいます。
また、AIによる監視も注目されています。顔認証や視線検出、音声解析などを組み合わせることで、人間では難しい異常の検知を自動化。不正の兆候をリアルタイムで察知し、記録することが可能です。
さらに、ブラウザロックの導入も効果的です。試験中に他のアプリケーションやWebページにアクセスできないよう制限することで、インターネット検索などの不正を防ぎます。
不正を完全にゼロにするのは難しいかもしれませんが、複数の対策を組み合わせることで、リスクを最小限に抑えることは十分可能です。
IBTでは、試験官が受験者の環境を完全に把握することが難しく、なりすましやカンニングといった不正行為のリスクが高まります。AI監視やブラウザロックなどの技術を駆使しても、受験環境が完全に統一されない以上、一定の限界があるのが現実です。
その点CBTは、同一会場・同一システム下での受験が行えるため、試験監督の目が届きやすく、AI監視との併用によって不正行為の抑止力が格段に高まります。
重要度の高い試験や資格認定など、公正性が問われる場面では、CBT形式を選ぶことが不正リスクの低減につながります。
導入までの流れと成功のポイント
オンライン試験を導入する際は、スムーズな運用に向けた準備が欠かせません。以下に、基本的な流れを紹介します。
まずは要件ヒアリングを行い、試験の目的や運用ルール、不正防止の方針などを明確にします。次に、試験データや受験者情報の登録を行い、試験実施の土台を整えます。
続いて、受験者に対して受験環境の提示を行い、PCスペックやインターネット環境、必要なデバイスについて説明します。試験当日に混乱を招かないよう、事前の操作体験(リハーサル)を設けることも重要です。
試験当日は、サポート体制の確保が不可欠です。受験者からの問い合わせやトラブルに対応できるよう、サポート窓口を設けておきましょう。終了後は採点およびフィードバックを実施し、必要に応じて改善点を洗い出します。
これら一連の流れを確実に実行するためには、信頼できる試験システムの選定が鍵を握ります。たとえば「スマート入試」では、顔認証やAI監視など高度な不正対策機能を搭載しており、インストール不要で簡単に導入できる点が特長です。
なお、システム導入にあたっては、CBTを前提とした構成のほうが運用が安定するケースもあります。特に大規模な試験を想定している場合や、受験者側のITリテラシーにばらつきがある場合には、CBTによる運営が効果的です。現場におけるトラブル対応も迅速に行えるため、初めてオンライン試験を導入する企業・団体にとっても安心材料となります。
CBTの導入が進む理由とは?試験制度としての信頼性の高さ
近年、オンライン試験の主流としてCBTの導入が加速しています。その背景には、従来の紙試験に代わる新たなスタンダードとしての信頼性の高さがあります。CBTは、試験会場という統一された環境下で実施されるため、受験者全員がほぼ同一の条件で試験に臨める点が大きな強みです。
また、事前に端末の整備やセキュリティ設定ができることで、機材トラブルや通信エラーといったリスクを最小限に抑えられます。さらに、不正防止策として、監督官による目視監視とAIによる映像・行動解析を組み合わせることで、より厳密な運用が可能です。IBTのように受験環境に左右されにくく、特に国家資格や社内昇格試験といった高い公平性が求められる試験では、CBTの導入が有効な選択肢となるでしょう。
まとめ
オンライン試験は、受験者の利便性や試験運営の効率化を実現できる新たな試験手法です。しかしながら、コスト削減や感染症対策にも効果がある一方、不正防止やシステムトラブルへの対処といった課題にも向き合う必要があります。
その意味で、会場受験型であるCBTは、技術的・運用的な観点から見ても信頼性が高く、不正リスクの低減に適した方式といえます。IBTと比較しても、実施のハードルはやや高いかもしれませんが、その分、質の高い試験運営が可能です。
オンライン化のメリットを享受しつつ、公平で正確な評価を行うには、CBTが現実的かつ有効な選択肢であると言えるでしょう。
-
 引用元:https://cbt-s.com/
引用元:https://cbt-s.com/
国内最大の導入実績を持つCBTソリューションズのCBTサービスは、試験の申込から受験料の回収、全国でのCBTによる試験の実施、採点、結果発表、コールセンター等、試験業務の全てを業界No.1の水準でサービス提供可能。
国家試験から有名団体まで200以上の試験が現在も実施されており、国内最大の80%以上の導入シェアを持つ実績十分の企業です。会場も47都道府県の全ての主要都市に国内最大の360の会場を展開中。受験者は一年中好きな場所で試験を受けられます。