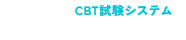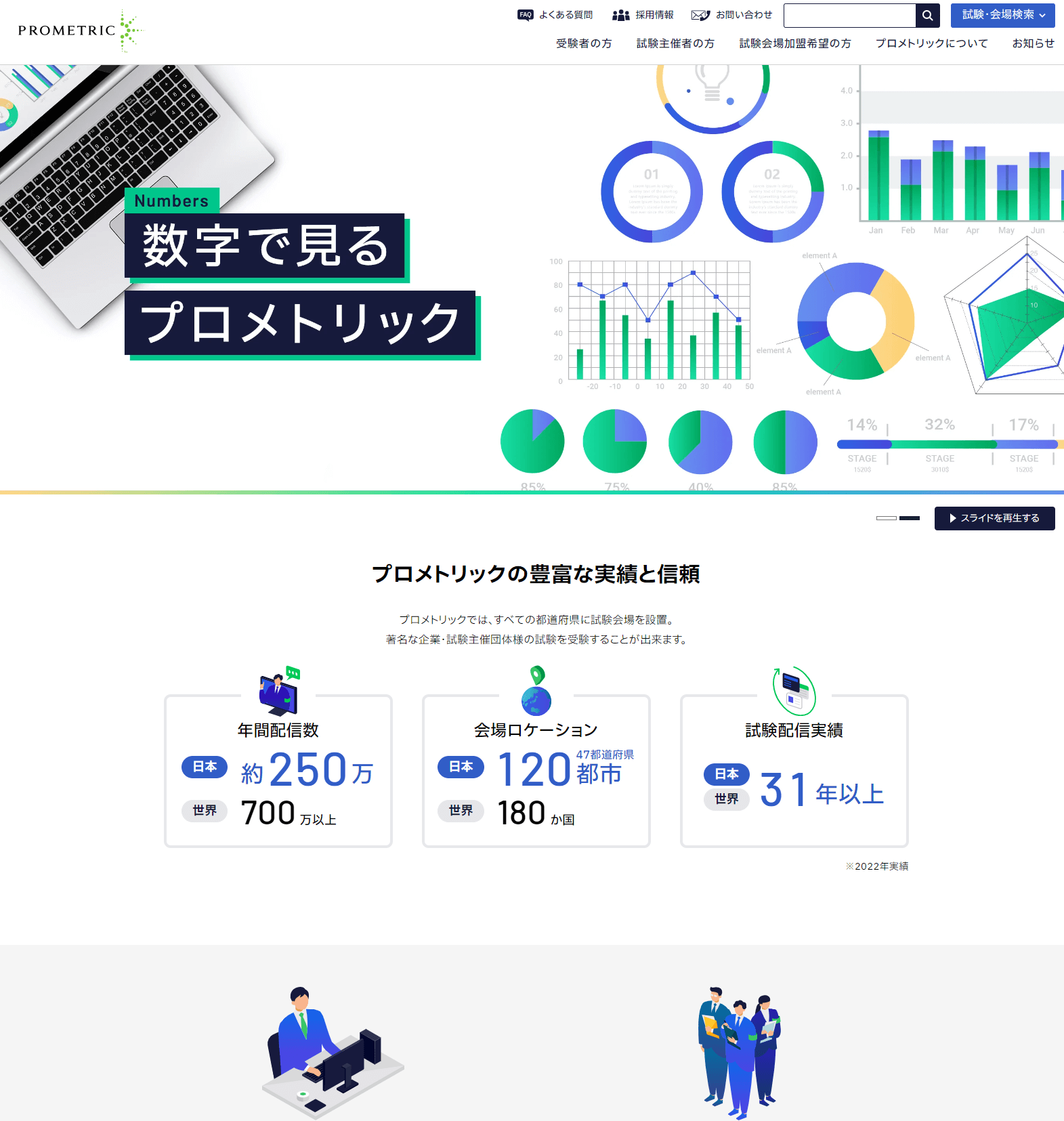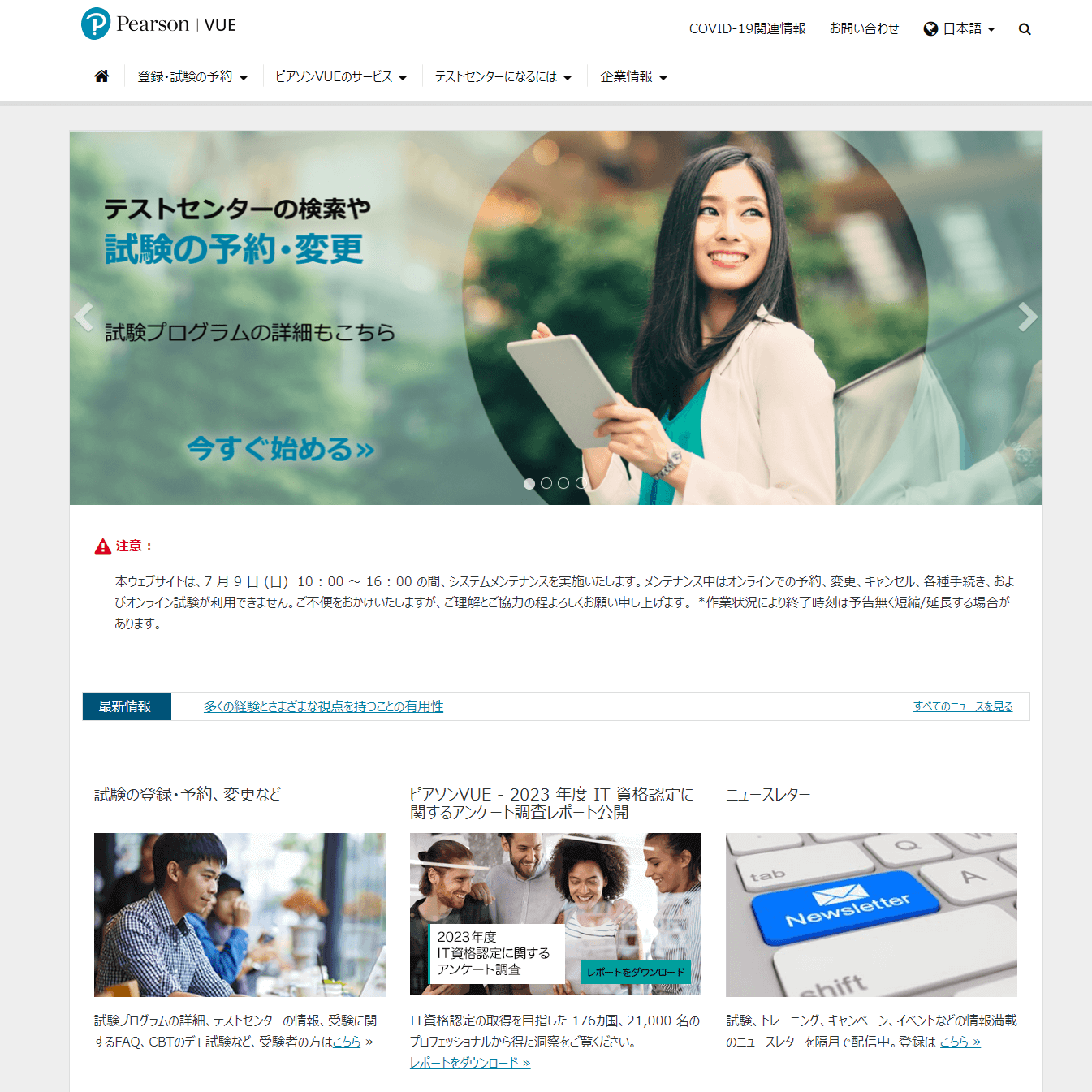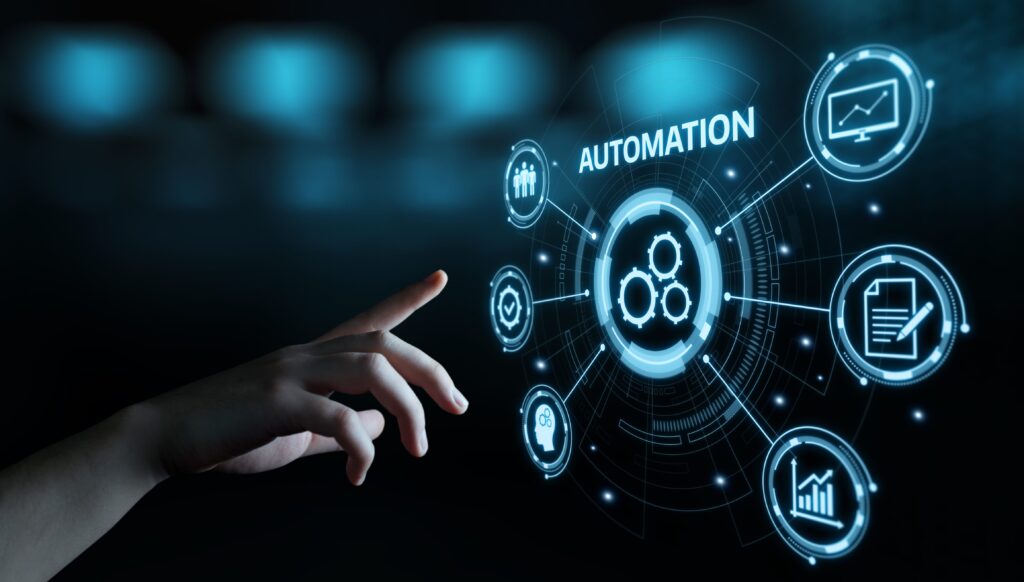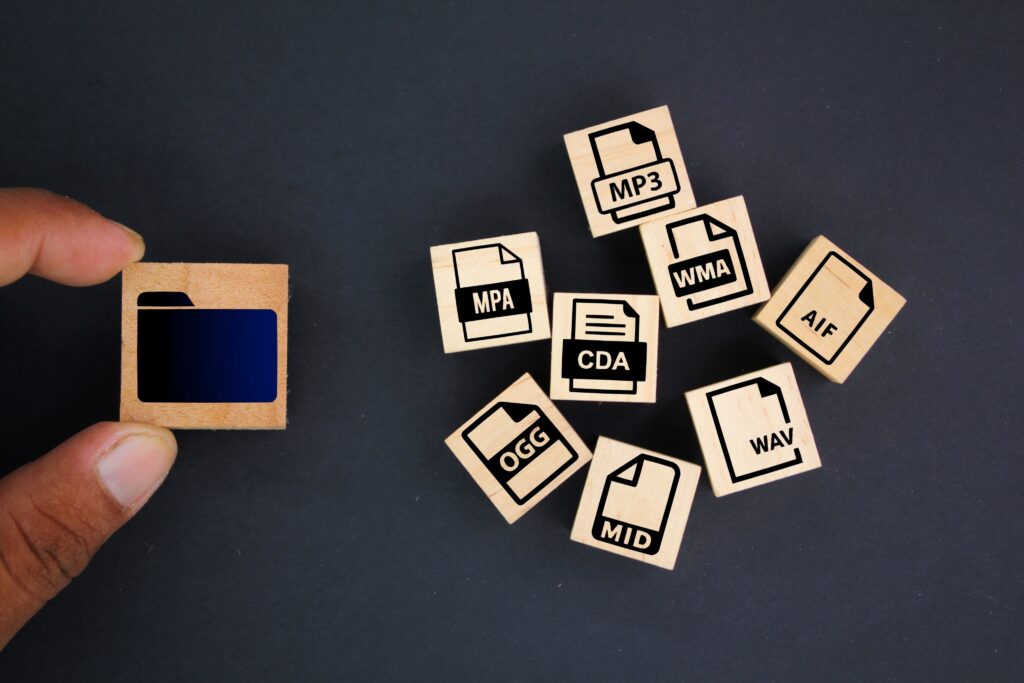
CBT(Computer Based Testing)は、従来の紙試験に比べて柔軟な出題形式が可能です。とくに、音声や動画を取り入れた問題を活用することで、より実践的で多角的な能力評価ができます。本記事では、CBTが音声や動画を使った問題に対応できるのか、その具体的な出題形式や導入時の注意点について解説します。
CBTは音声・動画を使った問題にも対応可能なのか
結論からいうと、CBT方式では音声や動画を使った問題が十分に出題可能です。むしろ試験がコンピュータを介して行われるため、紙媒体よりも親和性が高いといえるでしょう。
幅広い出題表現が可能
テキストのみの試験では表現が難しかった問題も、音声や動画を取り入れることで実現できます。たとえば、受験者に対して画面上で操作を求める問題や、リアルな場面をシミュレーションした問題も作成可能です。
これにより、従来では測定が難しかったスキルも評価できるようになります。
リスニング試験に適している
語学検定などで出題されるリスニング問題は、CBTとの相性が非常によい形式です。
従来の紙試験では、会場全体で一斉に音声を流す形式が一般的でしたが、CBTでは受験者ごとに自分のタイミングで再生し、解答を進めることができます。これにより、集中力を保ちながら効率的に試験を受けられるのがメリットです。
受験者の能力をよりくわしく評価できる
動画や音声を使うことで、単なる知識ではなく実践的なスキルや応用力を評価することが可能になります。たとえば、医療分野では診断映像を見て判断する問題、販売分野では接客シーンを評価する問題など、現場に即した形式で能力を可視化できます。
結果として、受験者の実力をこれまで以上に詳細に測定できる点が大きな利点です。
CBTで対応可能な出題形式の種類
CBTの大きな特徴は、出題形式の多様性にあります。音声や動画を組み込むことで、従来の筆記試験では実現が難しかった表現が可能となり、受験者の実力を多角的に評価できます。
各ベンダーによって実現できる範囲は異なりますが、代表的な形式を見ていきましょう。
音声のみの出題例
たとえば、言語能力試験では、さまざまなアクセントや速度で話される音声を流し、受験者のリスニング能力を測定できます。紙試験のように全員一斉に聞く必要がないため、個別対応が可能です。
動画のみの出題例
医療系試験では、超音波エコーやレントゲン画像などを動画で提示し、診断能力を問う問題が作成できます。実際の臨床に近い状況を再現でき、多様な症例に対応できる力を評価できます。
また、技能試験では機械操作や特定の作業手順を動画で示し、正しい操作かどうかを判断させる問題も可能です。最新技術を反映させた試験内容を取り入れることで、実務に直結した評価ができます。
音声ありの動画の出題例
動画を使った出題では、販売員向け試験で活用されています。これは接客シーンを音声付きの動画で再現し、受験者に改善点を答えさせる形式です。映像と音声を組み合わせることで、受験者の理解度をより正確に測ることができます。
CBTで動画や音声形式の問題を出題する際の注意点
メリットが多い一方で、CBTに音声や動画を導入する際にはいくつか注意点があります。試験の公平性や利便性を保つためにも、事前に考慮すべきポイントを整理しておきましょう。
メモが取れないことを考慮した設計
CBTでは紙の問題用紙が配布されないため、問題文に直接メモを書き込むことができません。動画や音声を使うと内容が複雑になる場合も多いため、受験者がメモなしで対応できるように設計する必要があります。
あるいは、試験運営側でメモ用紙と筆記用具の使用を認めるといった工夫も求められます。
音声問題にはヘッドホンが必須
リスニング問題を出題する場合、受験者ひとりひとりがヘッドホンを使用できる環境を整えなければなりません。とくに複数会場で試験を実施する際には、すべての会場で同等の品質のヘッドホンをそろえる必要があります。
音質の違いによって有利・不利が生じないよう、同規格の機材を用意することが重要です。
通信量への配慮
動画は音声に比べて通信量が多く、会場のインターネット環境やPC性能に影響を与える可能性があります。場合によっては映像が再生できない、途中で止まるといったトラブルが発生する恐れもあります。
そのため、映像の画質を調整して通信量を抑える、事前に環境テストを行うなどの対策が必要です。
再生設定のルール決定
音声や動画を試験で再生する場合、再生方式のルールを明確にすることが大切です。
一般的なリスニング試験では、一定時間後に自動的に再生が始まる自動再生方式がほとんどです。これなら統一性は保てますが、不意の再生によって受験者が焦る可能性もあります。
反対に、受験者が準備できたタイミングで再生できる任意再生方式もあります。柔軟性が高い反面、試験時間を無駄にしないよう注意が必要です。
さらに再生回数の設定も重要です。1回限りの再生なら、集中力を求める出題が可能ですが、再生後にメモを取る時間を設けるとよいでしょう。
複数回再生なら細部を確認したい問題に適しており、公平性を高められます。試験の目的や難易度に応じて、これらのルールを慎重に設計することが不可欠です。
まとめ
CBTでは音声や動画を使った問題に対応可能であり、紙の試験よりも柔軟な出題形式を実現できます。語学試験のリスニングや医療・技能試験における動画問題、販売員試験の接客シーン評価など、幅広い活用が可能です。一方で、メモの取り扱い、ヘッドホンの準備、通信量への配慮、再生方式のルール設定など、導入時には注意点も多く存在します。これらを適切に設計することで、受験者にとって公平で利便性の高い試験環境を提供できるでしょう。音声や動画を活用したCBTは、これまで以上に実践的で応用的な能力を評価できる手段として、今後ますます重要な位置を占めていくと考えられます。
-
 引用元:https://cbt-s.com/
引用元:https://cbt-s.com/
国内最大の導入実績を持つCBTソリューションズのCBTサービスは、試験の申込から受験料の回収、全国でのCBTによる試験の実施、採点、結果発表、コールセンター等、試験業務の全てを業界No.1の水準でサービス提供可能。
国家試験から有名団体まで200以上の試験が現在も実施されており、国内最大の80%以上の導入シェアを持つ実績十分の企業です。会場も47都道府県の全ての主要都市に国内最大の360の会場を展開中。受験者は一年中好きな場所で試験を受けられます。